ルートプラン(その2)
CPの決め方
実際にオリエンテーリングをするとき、どのような地点をCPにすればよいのでしょうか? 実は、CPにすべき地点は、2種類あります。
1つ目は、進行方向が変わる地点です。
図1を見てください。
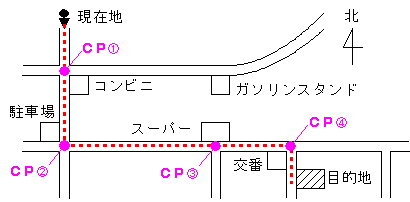 |
| 図1 |
この図でいうと、CP②とCP④が該当します。
進行方向が変わる地点はきわめて重要な場所です。
なぜなら、この場所を間違えると必ず道に迷うからです。
例えば、図1のCP①に着いたときに、この十字路をCP②と間違えたらどうなるでしょうか。
ルートプランでは、CP②で東(進行方向に対し左)に曲がることにしています。
従ってCP①をCP②と勘違いした場合には、CP①で左折してしまい、道に迷うことになります(図2)。
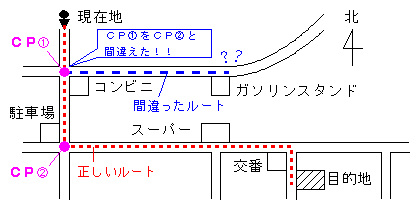 |
| 図2 |
進行方向が変わる地点は、必ずCPにする必要があります。
CPにすべき地点の2つ目は、ルート上のわかりやすい場所です。
図1ではCP①とCP③が該当します。
舗装道路どうしの交差点など、わかりやすい地点は、確実にその地点に到達したことに気付くことができます。
このようなCPを決めておけば、急いでいても自分が今地図上でどこにいるのか確実に知ることができ(どこまで来ているのかがわかり)、自信を持って次のCPへ向かうことができます。
CP①をCPに決めておくことで、図2のようにCP①をCP②と間違えるようなことがなくなるのです。
また、オリエンテーリングでは、自分がいる位置に自信があるかどうかが巡航スピードに多大な影響を与えます。
不安なときは、無駄に地図を確認してしまい走ることに集中できなかったり、CPを確実に見つけたいという意識からスピードが落ちたりするのです。
迷わず、速く進むために、ルート上のわかりやすい場所も、積極的にCPとして活用しましょう。
情報の複合化
ルートプラン(その1)のページで述べたとおり、オリエンテーリングでは、明確なCPを決めてルートプランを立てる必要があります。 明確なCPとは、実際に現地に行ったときに確実に見つけられるCPということです。 では、どのようなCPなら確実に見つけられるのでしょうか?
図3を見てください。
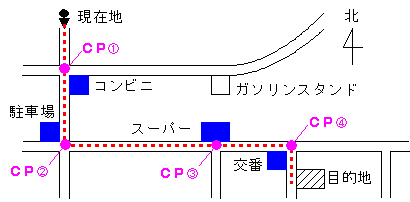 |
| 図3 |
CP①を例に取ると、これまでこの地点は「十字路」とだけイメージされてきました。
しかし地図をよく見ると、この地点には「コンビニ」があります。
CP①は単なる「十字路」ではなく、「道路を渡った左手の角にコンビニがある十字路」とイメージできます。
つまり、とある1地点を、単一の情報(「十字路」)だけではなく、情報を複合化(「道路を渡った左手の角にコンビニがある十字路」)させることで、より明確にイメージできるのです。
情報を複合化させ、より明確にCPをイメージすることで、他の地点との区別が容易になります。
例えば、情報を複合化させていれば、図2のようにCP①をCP②と間違えるようなことはありません。
CP①は単なる「十字路」ではなく「道路を渡った左手の角にコンビニがある十字路」です。
また、CP②も単なる「十字路」ではなく「道路を渡る手前の右手の角に駐車場がある十字路」です。
以前のように、両方のCPを単なる「十字路」としていたら、両者を混同するミスが生じます。
しかし、情報を複合化することで、CP①とCP②を明確に区別することができ、ミスなく正しいルートを進むことができるのです。
CP③、CP④も同様、ただの「T字路」とするのではなく、以下のように情報を複合化させてイメージすれば、両者を混同するようなミスは起こりません。
・CP③ = 「左手にスーパーがあるT字路」
・CP④ = 「右手手前の角に交番があるT字路」
以上のように、ルートプランは、道順を考えるだけではなく、適切なCPを決めることが大事です。 そして、CPは情報を複合化してイメージしましょう。 また、CPが確実に見つけられるよう、実際に現地を進むときにはCPをしっかりイメージし、次に行く場所をあらかじめ予測するようにしましょう。
次のページでは、いよいよO-MAPを用いて、ルートプランを立ててみましょう。


