ルートプラン(その1)
ルートプランとは
多くのみなさんは、日常生活において「地図を頼りに目的地へ行った」という経験をお持ちではないでしょうか。
そのようなときは、地図を見て目的地までの道順(ルート)を考えてから歩き始めたかと思います。
オリエンテーリングでも、現在地から目的地へ向かう前には、地図を見て目的地までの行き方を考えます。
この「目的地までの行き方を考える」ことを、ルートプランといいます。
オリエンテーリングでは、目的地(コントロールやゴール)は決まっていますが、目的地に着くためのルートは自由です。
しかし、できるだけ速く目的地に到達するためには、「良いルート」を考えなくてはなりません(実は「良いルート」が何かというのは難しい話になるのですが、その話は後ほど)。
では次の項目から、ルートプランの立て方について具体的に説明していきましょう。
ルートプランの立て方
図1を見てください。
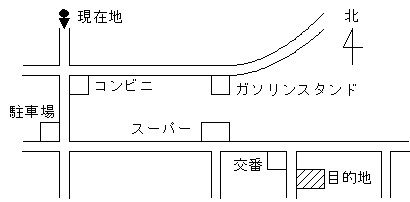 |
| 図1 |
この地図をもとに、現在地から目的地へ向かうためのルートプランを考えてみましょう。
この程度であれば、迷路を解く要領で地図上では簡単にルートを決めることができるでしょう。
つまり、図2の赤い点線で示したルートのように進めば、目的地にたどり着くことができるはずです。
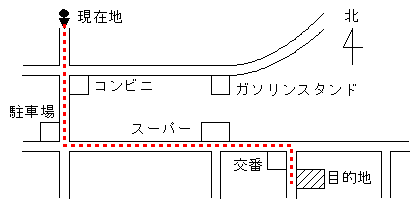 |
| 図2 |
しかし、迷路を解くように道順だけを決めた場合、実際に歩き始めると思うように目的の道順をトレースできないはずです。 例えば、左折しようと思っている交差点がなかなか現れず不安になったり、ひどいときには曲がるべき交差点ではなく1つ手前の交差点で曲がってしまったり、などという経験はないでしょうか。 なぜ、迷路を解くように道順だけを決めた場合は、不安になったり、道を間違えたりするのでしょう?
それは、チェックポイントが設定されていないからです。
チェックポイント(CPと略します)とは、ルートの途中で自分の居場所を確認するために、あらかじめ決めておく目印となる場所のことです。
図2をもう一度見てください。
ルートを考えただけでは、「どのような場所を通るのか」や「どこで曲がるのか」などが良く決まっていません。
そのため、「この道で良いのだろうか」や「この交差点で曲がって良いのだろうか」などの不安が生じるわけです。
そこでルートの途中に、CPを決めておき、実際に歩くときにはそのCPを確認しながら進むようにします。
図2のルートの場合、図3で示したようなCPを決めておき、実際に歩くときに確認しながら進むようにします。
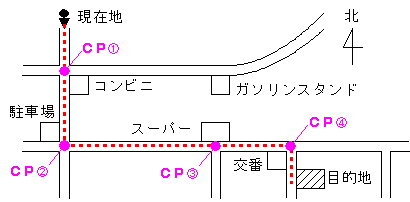 |
| 図3 |
具体的には、
「出発したら南に向かい、1つ目の十字路(CP①)を通り過ぎ、2つ目の十字路(CP②)を東に曲がる(進行方向に対して左です)。
道を東に曲がったら、1つ目のT字路(CP③)を通り過ぎ、2つ目のT字路(CP④)を南に曲がる(進行方向に対して右です)。
南に曲がるとすぐに、進行方向に対して左手に目的地がある。」
などと、ルートプランを立てます。
実際に歩くときには、事前に立てたこのルートプランに従って、CPを1つ1つ確認しながら進むようにすれば不安なく進むことができるのです。
このとき、「次に○○があるはずだ」と予測しつつCPを探すようにしながら進むようにしましょう。
予測せずに何気なく進んでいると、せっかく決めたCPを見逃してしまいます。
繰り返しますが、必ず「予測しながら」進むようにしましょう。
さて、これでルートプランはバッチリ、と言いたいところですが、そうはいきません。
先述のルートプランでは、オリエンテーリングをするのに不十分です。
確かに、町の中の道路であれば、先述のルートプランでも十分です。
しかし、オリエンテーリングは視界の悪い林の中で行われます。
道も、舗装された道路だけではなく、けもの道のようなわかりにくい道を辿る必要があります。
つまり、CPを単純に「十字路」などと決めただけでは、そのCPを見つけることができないことがしばしばあるのです。
見つけられないようなCPではCPとなりません。
CPはしっかり見つけられるように設定するべきなのです。
それでは、次のページではCPについてもう少し詳しく説明し、ルートプランについてより深く考えてみましょう。


